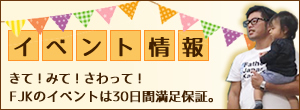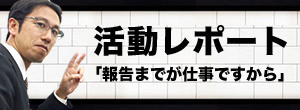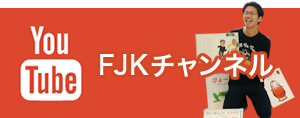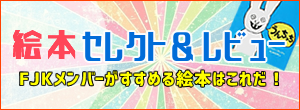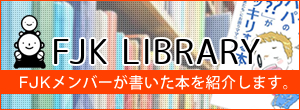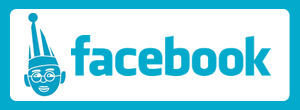選挙権が18歳からになった最初の総選挙が迫っています。
あちこちで若者の投票率をあげようと、いろんな呼びかけが行われています。
グラフは年代別の投票率を表したもの。※明るい選挙推進協会より
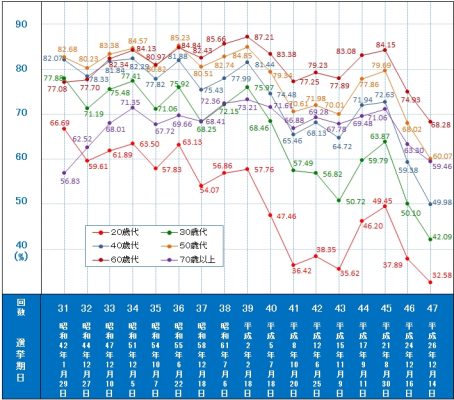
前回の衆議院総選挙、20代の投票率は33パーセント。
子育て世代である30代、40代の投票率も50パーセントを切っています。
20代より高いとはいえ、そのさらに上の50代・60代が60パーセント以上あるのと比べたら褒められたものではありません。
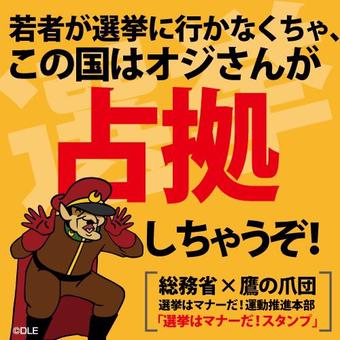
「子どもに期待してます」
という『大人』の言葉をきくたびに、子どもや若者に期待する前に『大人』である自分ができることやってる?と反問したくなります。
まず30代40代が投票に行くこと。
若者に期待するのはそれからです。
僕自身も恥ずかしながら20代のころは選挙に関心がありませんでした。
唯一関心を持った投票行動は2001年の郵政選挙。
今となってはこれも世間の風にあおられただけで、自分で考えてへんかったなぁと思います。
思い出してみると、僕が子どもの頃親や周りの大人から聞いた政治の話は、
「誰に入れても同じ」という投票の意味を否定する言葉でした。
そりゃ、興味もたんわな。
いや、僕も40代のおっさんになったからわかるんです。
政治の話題ってデリケートで、夫婦間ですることも面倒だし、世間でするなんてとんでもない。避けて通りたいです。
「誰に入れても同じ」と斜に構えたい気持ちにも、
(中二かよ!と突っ込みたい気持ちは横に置いて)共感します。
今も正直、ここでこの程度の話でも躊躇しながら書いてるくらいですから。
それでも、です。「父親として子どもに伝えたいこと」という意味合いでFJK副理事長として書きます。
ーーー
面倒くさいかもしれないけど、選挙のときくらいちょっとは政治を夫婦の話題にすべきです。
未来の有権者のために。
ウチは妻と僕で政治に対する感覚が大分違うので、選挙の時ちょっとくらいの話でも結構面倒くさくなってました。
それでも話題にできるのは3つの点で一致しているから。
・政治の話は大事
・支持政党が違っても大丈夫
・選挙には子どもも連れて家族全員で行く
最近はお互い意見を戦わせずに、
「そやな、そっちはそう思ってんねんな」
と、違いを確認するだけで終わってます。
正直夫婦で議論って、メリットよりデメリットが大きい。
お互いの違いを知るだけで十分です。
それはそれ、これはこれ。
政治に対する意見が違っても家族はやっていけるんです。
このスタンス自体がわが子に対する教育だと僕は考えています。
もう一つ、今回の選挙で夫婦が一致したこと。
絶対選ばない政党2つが同じでした。
これが一致するのはウチでは珍しいです。
ちなみに、誰に・何党に入れたのかはお互いに聞きません。

総務省の去年のキャンペーン。
「選挙はマナーだ!」
今回こそ大々的にやってほしかったな。
和田 憲明
最新記事 by 和田 憲明 (全て見る)
- 【告知】FJK的オンライン読書会#3 4/16(金)21:00~22:30 - 2021年4月11日
- FJK映像制作サロンはじめました - 2020年8月30日
- 警備員さんはアグレッシブ - 2019年4月25日
- 通学路の女性はロールモデルだった - 2019年4月24日
![[FJK] NPO法人ファザーリング・ジャパン関西公式サイト](http://fjkansai.jp/img/logo.png)